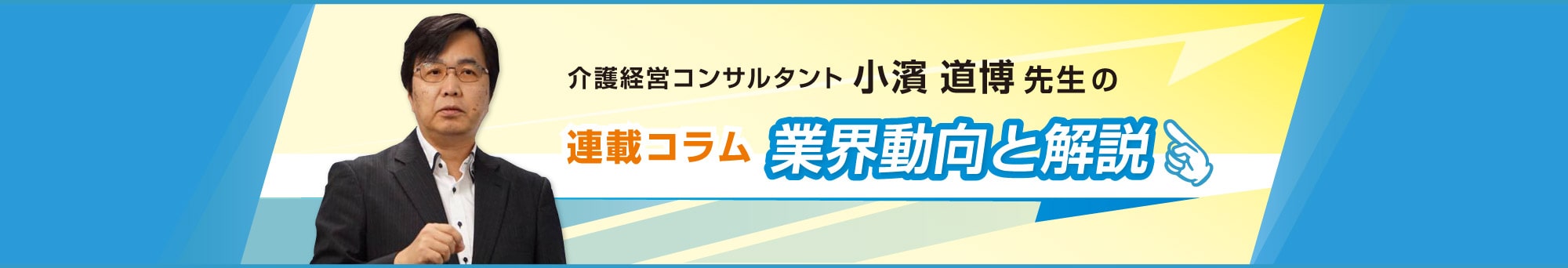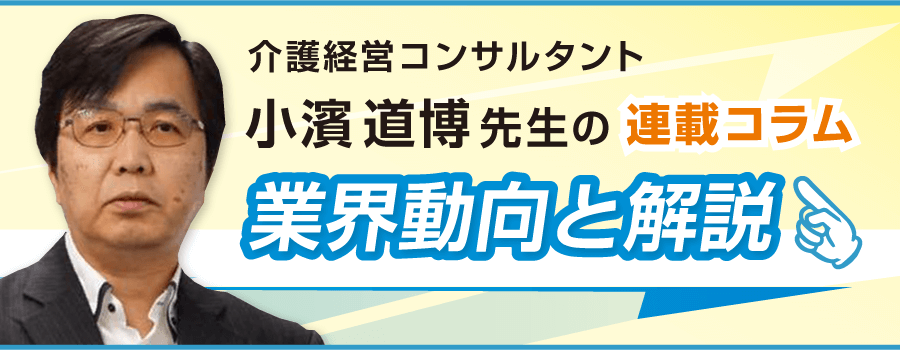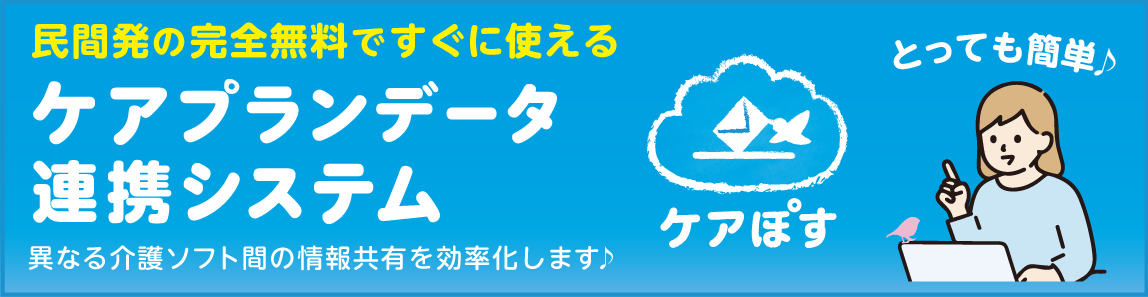令和7年度へ向けて、今、ケアマネジャーが把握しておくべきこと
次期制度改正に向けて、厚生労働省においてケアマネジャーとケアプランの在り方について議論されている内容を整理すると、現状の課題と将来の方向性がより明確になる。
ケアマネジャーは、介護保険サービスの利用者と事業者、医療機関をつなぐ調整役として重要な存在であるが、現場で直面している深刻な課題について、その現状を解説する。
1.業務負担過多の対策
まず、業務負担の過多が挙げられる。
ケアマネジャーの業務は過剰とも言えるほど広く、ケアプランを作成するだけではない。例を上げると、利用者宅への訪問、家族や関係機関との調整、医療や福祉機関との連絡業務などがある。さらに、制度上必要とされる書類作成も大きな負担となっており、これらに費やす時間や、その他のシャドーワークの存在が労働環境に悪影響を与えている。多忙を極める日常が、やがて慢性的な疲労やストレスの原因となっている。この問題は、特にケアマネジャー1人当たりの担当者利用者数が多い地域や施設で顕著である。
2.報酬体系の問題
次に、報酬体系がケアマネジャーの業務量や専門性に見合っていない点も大きな課題である。
これにより、ベテランのケアマネジャーほど負担が多く収入が横ばいであるため、モチベーションの維持が困難となる場合があり、離職するケースが増えている。結果として経験やスキルの不足が現場のケアに悪影響を及ぼしていることがある。
3.人員不足
それに加えて、ケアマネジャーの人員不足が深刻である。
介護保険制度が施行された当初に比べて、利用者の数は増加の一途をたどっているものの、ケアマネジャーの数はそれに比例して増加していない。これにより、1人あたりが担当する利用者数が増加し、より多くの業務を遂行する状況が続いている。その結果、時間的・精神的な余裕を捉え、サービスの質を十分に確保することが難しいというジレンマに直面している。
4.利用者によりそい公平性と効率性を高めるジレンマ
さらに、介護保険制度の頻繁な改正がケアマネジャーに過剰な負担を与えている現実もある。
例えば、利用者負担や報酬制度の変更、新たな認定基準の導入などにより、ケアマネジャーはその都度、新しい制度への対応に迫られる。このような制度変更は、利用者にとっての公平性や効率性を高める目的があるが、ケアマネジャーの業務はさらに複雑化し、負担を増加させている。新しいルールや基準に迅速に対応する必要があるが、現場では制度改正に関する十分な情報共有や教育が行っていないことが多く、混乱が生じている。
5.利用者ニーズの変化
利用者のニーズが多様化・重度化している点も課題である。
認知症や複合疾患を持つ利用者が増加する中で、ケアマネジャーには高度な専門性や調整能力が求められている。しかし、それに対応するための研修やサポート体制が不足している。
これらの複合的な課題は、ケアマネジャー自身の健康や働きがいにも影響を及ぼしている。ケアマネジャーの必要性が一般社会では十分に認識されず、その結果、感謝や理解が得られにくいと感じるケアマネジャーも多い。このような状況を改善しなければ、介護サービス全体の質の低下につながる懸念がある。
6.ケアプランの運用課題
ケアプランは、利用者の生活を支えるための具体的な介護サービスの計画として重要な役割を果たすが、その作成プロセスや運用にも課題がある。また、ケアプランの質についても議論がされている。
現状のケアプラン作成は、ケアマネジャーの経験や主観に依存する部分が多く、科学的な根拠に基づく介護(エビデンスベースドケア)が十分に反映されていない。
これを改善するために導入されたLIFE(科学的介護情報システム)は、利用者の状態やサービスの効果を数値的に評価し、ケアプラン改善の参考データを提供する役割を担っているが、現場での活用には課題が残されている。担当事業所の負担が大きいことや、フィードバックが具体的でないことが原因で、十分な効果を発揮していない状況がある。さらに、利用者との対話を重視するために、LIFEを活用した科学的データに基づく判断をどのように組み込むかが重要なテーマである。
画一的なケアプランではなく、利用者の価値観やライフスタイルに応じた柔軟な計画が求められる中で、データ活用と個別性の両立が課題となっているのだ。
7.検討されている改善策とは
以上の現状の課題を踏まえて、次期制度改正に向けて、ケアマネジャーとケアプランに関する以下のような改善策が検討されている。
①ケアマネジャーの業務環境改善
ケアマネジャーの業務負担を軽減するために、ICTの活用や業務効率化のためのツール導入が推進されている。また、報酬体系の見直しにより、ケアマネジャーのモチベーション向上と定着率の向上を図ることも重要な検討課題だ。
②資格更新認証の強化
5年ごとの資格更新時に提供される研修内容を現場のニーズに合わせたものに見直し、更新が基本的な手続きだけに終わらないようにする必要がある。ケアマネジャーの負担を軽減するための支援策も検討されている。
③ケアプランの利用者負担導入の慎重な検討
利用者負担を導入する場合には、低所得者や重度介護者への配慮を徹底することが求められる。例えば、結果に応じた負担額の設定や決定次第では、負担が過大にならないよう配慮する必要がある。
④LIFEの活用促進
LIFEのデータ入力負担を軽減するため、入力支援ツールやAI技術の活用が進められている。また、フィードバック内容を現場で活用しやすい形に改善し、ケアプラン作成における実効性を高める取り組みが求められている。
⑤利用者本位のケアプラン作成
科学的データと利用者の価値観やニーズを融合させたケアプランの作成が必要である。そのためには、ケアマネジャーが利用者との対話を十分に確保できる時間的余裕を持つことが重要であり、これを可能にする環境整備が必要となっている。
8.結論
次期制度改正では、ケアマネジャーの負担軽減、スキル向上、ケアプランの質向上、LIFEの有効活用、そして利用者負担の適正化が中心の課題となっている。
これらの取り組み、科学的根拠に基づいたケアを推進しなければならない。また、利用者のための多様なニーズに応える柔軟な制度設計が求められている。これにより、介護保険制度の持続可能性を確保しつつ、利用者にとって安心できる生活支援を実現することが目指されている。
著者プロフィール
小濱 道博 氏
小濱介護経営事務所 代表
C-SR 一般社団法人介護経営研究会 専務理事
C-MAS 介護事業経営研究会 顧問
昭和33年8月 札幌市生まれ。
北海学園大学卒業後、札幌市内の会計事務所に17年勤務。2000年に退職後、介護事業コンサルティングを手がけ、全国での介護事業経営セミナーの開催実績は、北海道から沖縄まで平成29年 は297件。延 30000 人以上の介護業者を動員。
全国各地の自治体の介護保険課、各協会、介護労働安定センター、 社会福祉協議会主催等での講師実績も多数。「日経ヘルスケア」「Vision と戦略」にて好評連載中。「シルバー産業新聞」「介護ビジョン」ほか介護経営専門誌などへの寄稿多数。ソリマチ「会計王・介護事業所スタイル」の監修を担当。